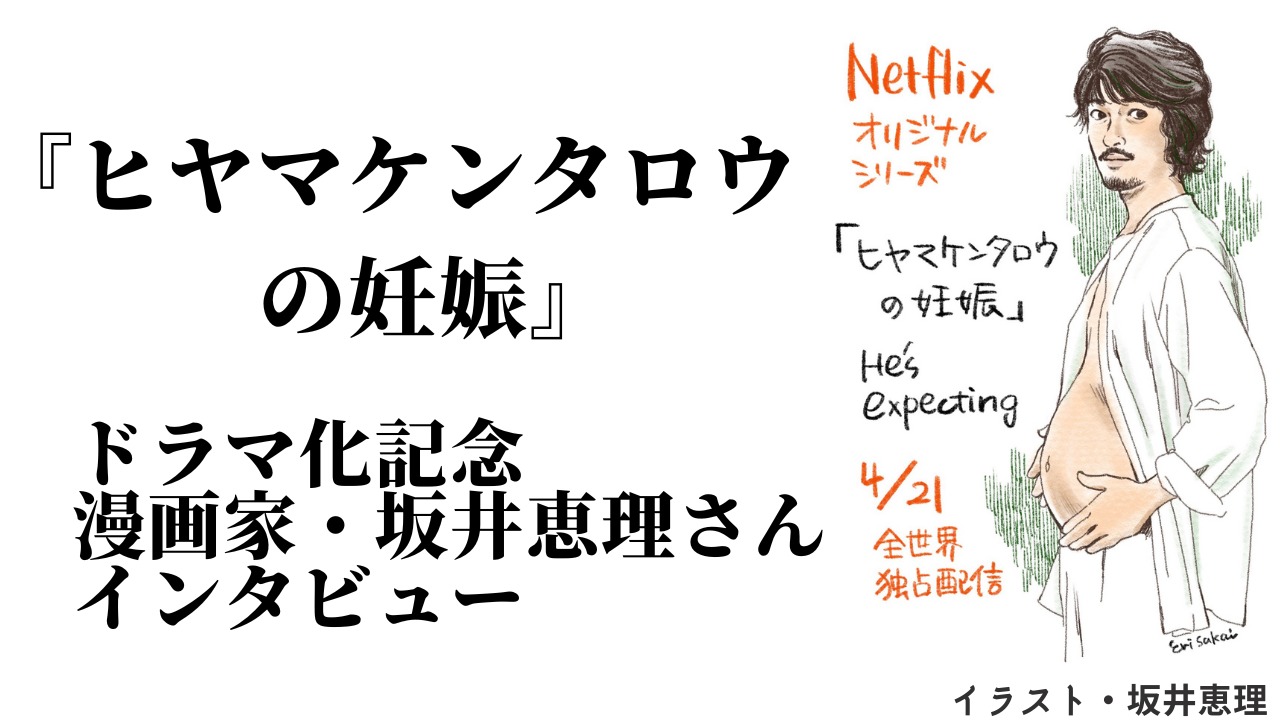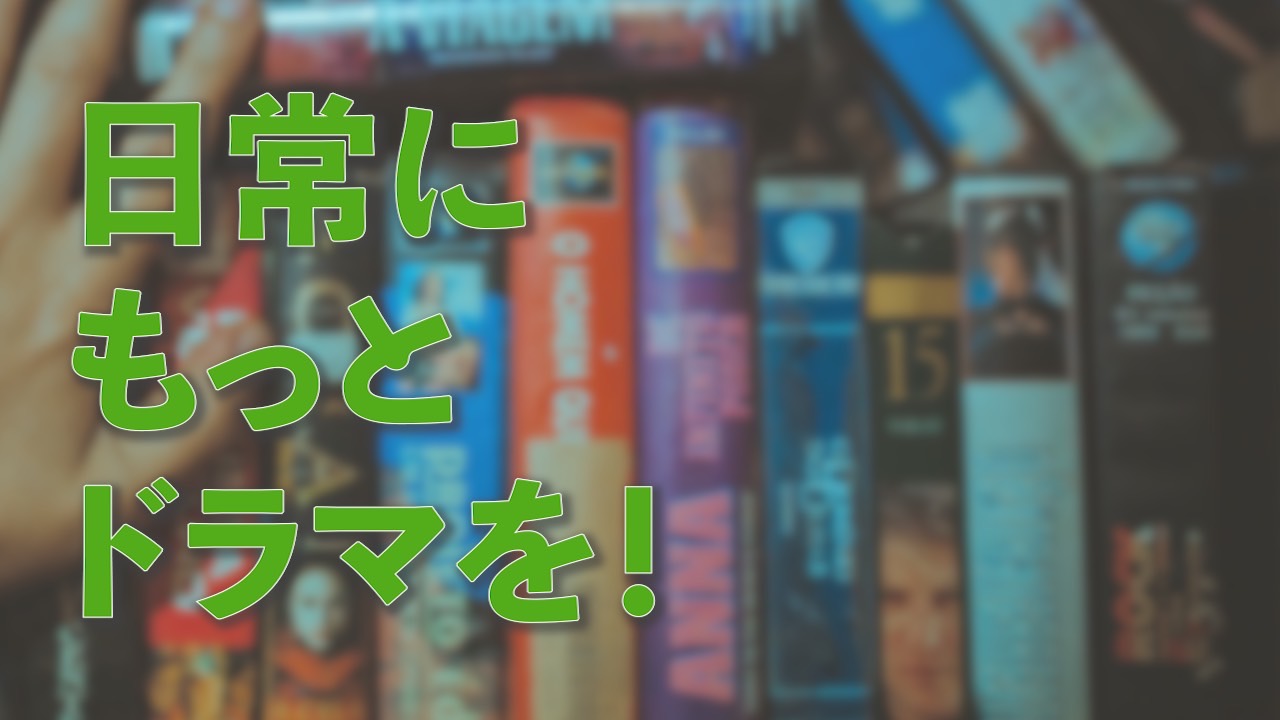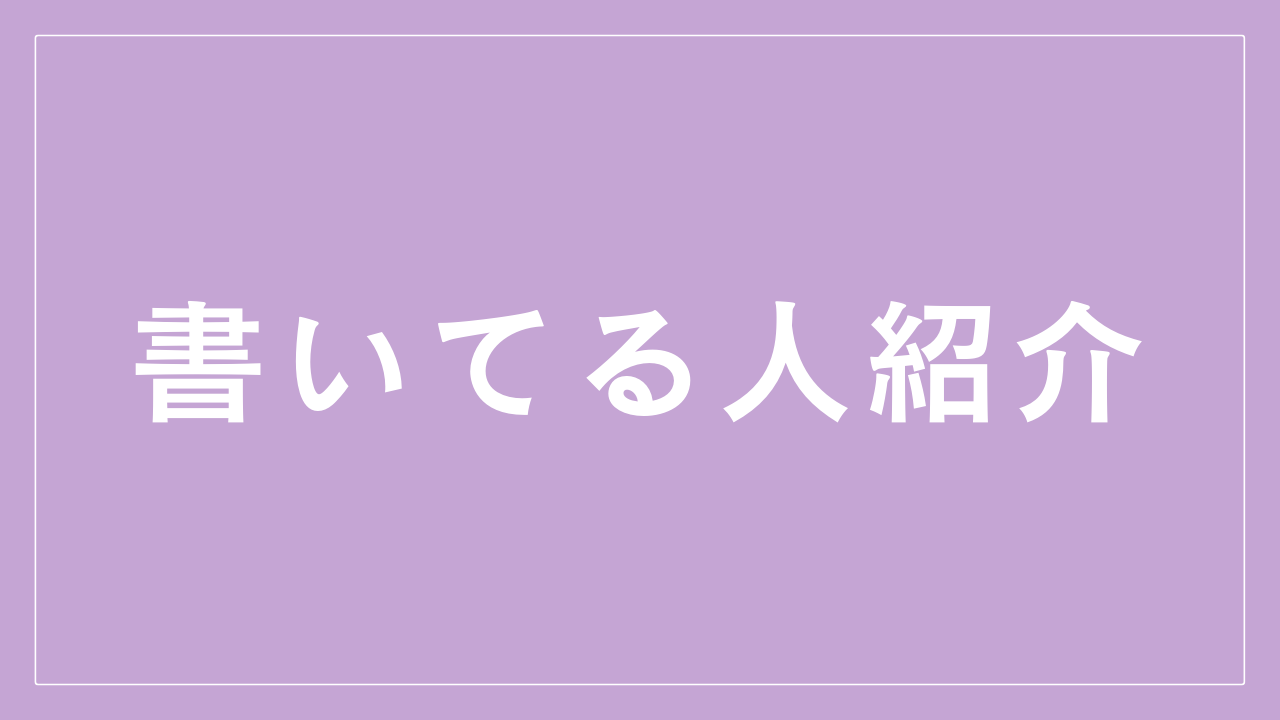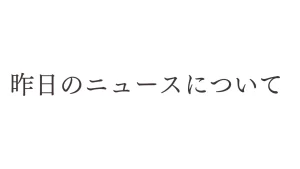昔から自分の髪が大嫌いだった。一目で「ガイジン」とわかるチリチリの赤毛は、いつだっていじり──いや、ヘイトの対象だったから。
中学受験で親の決めた花嫁育成お嬢様学校へ入学した直後くらいに、1泊2日の泊まり込み社会科見学的なイベントがあった。朝、ヘアアイロンで必死に癖を伸ばすぼくを見ていた同級生が、執拗にその様子を揶揄ってきたのを今でもよく覚えている。「チカゼさ、朝必死に寝癖直そうと頑張ってるのに全然直せてなくてめっちゃウケた〜」みたいに。数日経ってもネタにされ続け、それを引き攣り笑いで流していた数日間を、たぶんぼくは一生忘れない。
ぼくは、日本と韓国とロシアの3カ国にルーツを持つ。出生時の国籍は韓国で、つまるところぼくは在日コリアンとしてこの世に生を受けた。現在は帰化してしまっているので、「元在日コリアン」と表現したほうが適切だろうか。そしてぼくは親の意向で、多くの在日コリアンが持つ「通名」と呼ばれる日本人ふうの名前ではなく、戸籍上の本名──即座に「韓国人か中国人」だとわかる名前を当時は名乗らされていた。
癖毛は、おそらくロシアのほうのルーツに因るものだ。当時ミックスルーツであることは自分自身も知らなかったので、彼女たちの揶揄いがレイシズムに基づくものだったのかはわからない。ただ動機がどうであれ、癖毛への揶揄いは「ヘイト」であり「差別」であり、「ルッキズム」である。
ヘイトが激化し最終的に退学したのち、ぼくは共学の校則ゆるゆるな中高一貫校に転校した。中2の秋、10月末の木曜日。時期も曜日も何もかもが半端だったから、15年以上前のことなのに昨日のように思い出すことができる。のびのびとした自由な校風は、ミリ単位でスカート丈のチェックが入る花嫁育成学校よりもずっとぼくに合っていた。なにより見かねた親が渋々折れて通名使用許可を出したため、「日本人」として新たな生活をスタートすることが可能になった。直接的な差別を受けずに日々を過ごせることは、精神の安寧に大きく影響した。
やがて定まった制服がないゆえに通学時の服装に困り始めたころ、クラスメイトから「古着だったら安いよ!」と原宿や高円寺、下北沢などに誘われた。それをきっかけに、ずるずると古着沼にハマっていった。定価では到底手が出ない価格帯のハイブランド、ラルフローレンやラコステ、ヴィヴィアンウエストウッドなんかのニットやスウェットが、お年玉や高校生のバイト代でも手が届く。ド派手なデザインも好むようになったくらいからだろうか、友人たちに「髪の毛は染めないの? 癖毛が嫌なら縮毛矯正したらどう?」とアドバイスされることが増えていった。
ぼくの育った家庭は、いわゆる機能不全家庭だ。両親は今で言うところの毒親で、暴力を振るうひとたちだった。世間体を死ぬほど気にする両親に、「染髪したい」などと申し出る勇気はとてもじゃないけどない。親が厳しいんだよね、とやんわり告げると、友人たちは「徐々に明るくしていけば大丈夫だよ!」と後押しをしてくれた。そんな流れで3年生に上がってすぐ、セルフでのカラーを決行した。そのころちょうど自分ひとりでもムラなく染められる泡タイプのカラー剤がマツキヨなんかに並び始めていたので、ぼくの染髪デビゥは容易かった。
錆びた10円玉みたいな色から、赤みを抑えたアッシュブラウンに変えるとあら不思議、たったそれだけでなんだかやたらと垢抜けて見えた。染めた翌日、友人たちから賛辞をもらい、廊下ですれ違った先生たちからも「染めたの?! 似合うじゃん!」と褒めそやされ、生まれて初めて自らの容姿を肯定的に捉えることができた。
それ以来カラーリングが常になっても、暖色系に挑戦することはなかった。癖毛を徹底的に伸ばすための3ヶ月に一度の縮毛矯正も、いつしか必須になっていた。まっすぐストンと落ちるストレートヘアに赤みを消したアッシュ系や、とことんまでにブリーチで色素を抜いたホワイト系ばかりに固執していたのだけれど。
つい1週間前、なぜだかぼくは、限りなくかつての地毛に近いレッドブラウンに染めて、くりくりのパーマをかけた。
というのも今年の2月、だいすきな若手俳優の1人であるティモシー・シャラメ主演映画『ボーンズ・アンド・オール』の映画レビューをとあるメディアで執筆したのだけれど、作中のティミーが赤いハイライトを前髪に入れていて、それに触発されたのだ。もっとティミーに近づきたい。憧れの彼のような、かっこよくて可愛くて儚げな、萩尾望都が描くような「少年」になりたい。──髪を赤く染めて、くりくりのパーマをかけたい。
そんな気持ちがむくむくと湧き出したことに、自分でも驚いていた。
ちなみに20代後半くらいから、どういうわけだか徐々に癖毛は落ちつき出した。朝起きると必ず爆発したみたいになっていたのだが、ストレートとは言えないまでも「癖っ毛」ともつかないまでに髪質が変容したのだ。それは幼いときからずっと、望んでいたものだったのに。ティミーはあっさりと、ぼくの過去の容姿コンプレックスを吹き飛ばした。
そんなこんなで美容師さんに理想と近いティミーの写真をいくつかLINEで送り付け、相談した結果、ぼくの骨格や肌色なんかに似合うようアレンジするかたちでカラー&パーマを決行していただくことになった。美容師さんには「暖色カラーも絶対お似合いになると思います!」と力強く言い切ってもらえた。
15歳からずっと髪を染め続けているので、自分の地毛が実際にどんな色だったかだいぶ忘れてしまっている。けれども施術が終わって鏡を見ると、えも言われぬ懐かしさがじんわりと胸を支配した。ああ、そうだ。たしかこんな感じだった。根本を見る限りでは子どものときほどぼくの地毛は赤みが強くないけれど、あのころ大嫌いだったくりくり赤毛の再生に、ふしぎと郷愁を覚えた。美しい、と素直に思えた。いいじゃん、この髪型。
もちろん人工的に作り出した色味とカールだから、本来の地毛とは異なる。それでも仕上ったとき、込み上げてくるものがあった。あのころ貶されてばかりいた自分を、そんな馬鹿みたいな価値観を愚かにも内面化して自己肯定感をすり減らしていた自分を、容姿への中傷で一時は醜貌恐怖症にまで陥ってしまった自分を、ルーツを心底憎んでいた自分を、まるごと抱きしめられた気がした。30歳を越えて、ようやく。
かつての、多感で傷つきやすくて、踏みにじられたやわらかな心の蘇生がひどく困難だったぼくへ。大丈夫、あなたは美しい。だれが不細工と貶しても、だれに誹られようとも、それは揺るぎない事実です。損なわれた精神を、地毛と正反対の色味と質感で取り戻そうともがいていた時間も含めて。生来とかけ離れた容姿を選択しようとも、限りなく近い姿に回帰しようとも、ぼくはぼくとして、絶対的に素敵なのだ。どうかそのことに、早く気付いて。