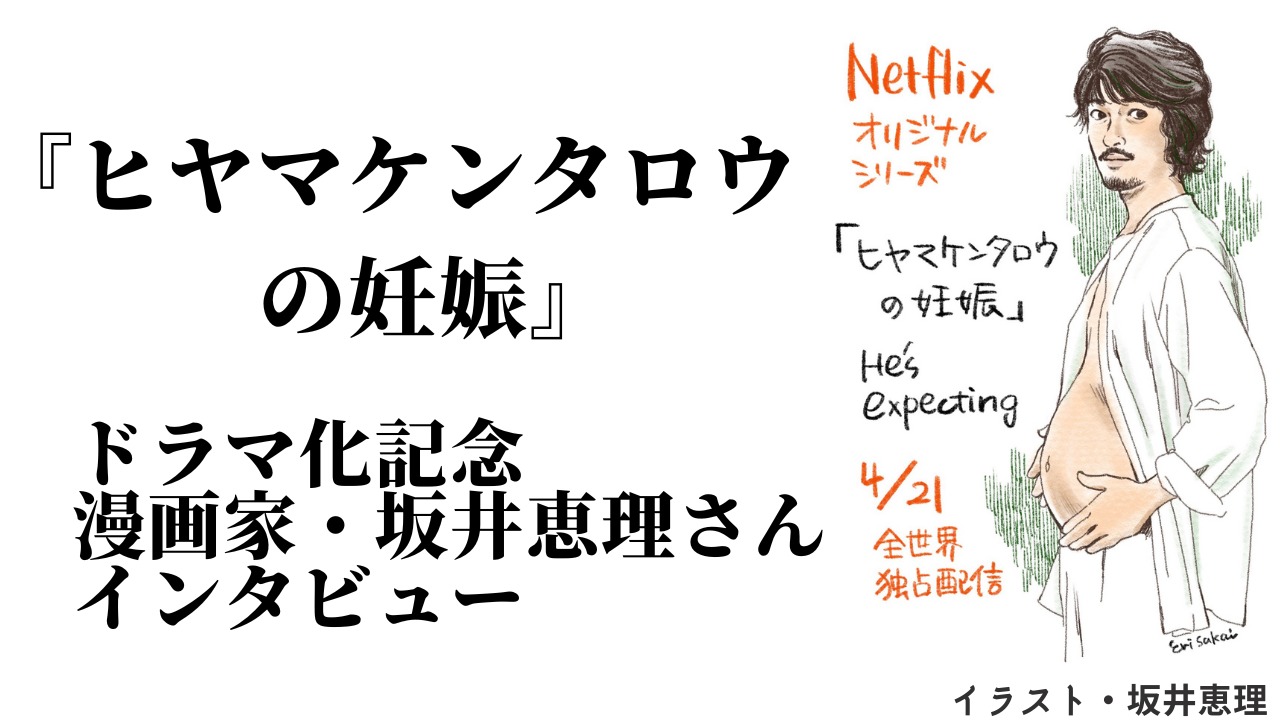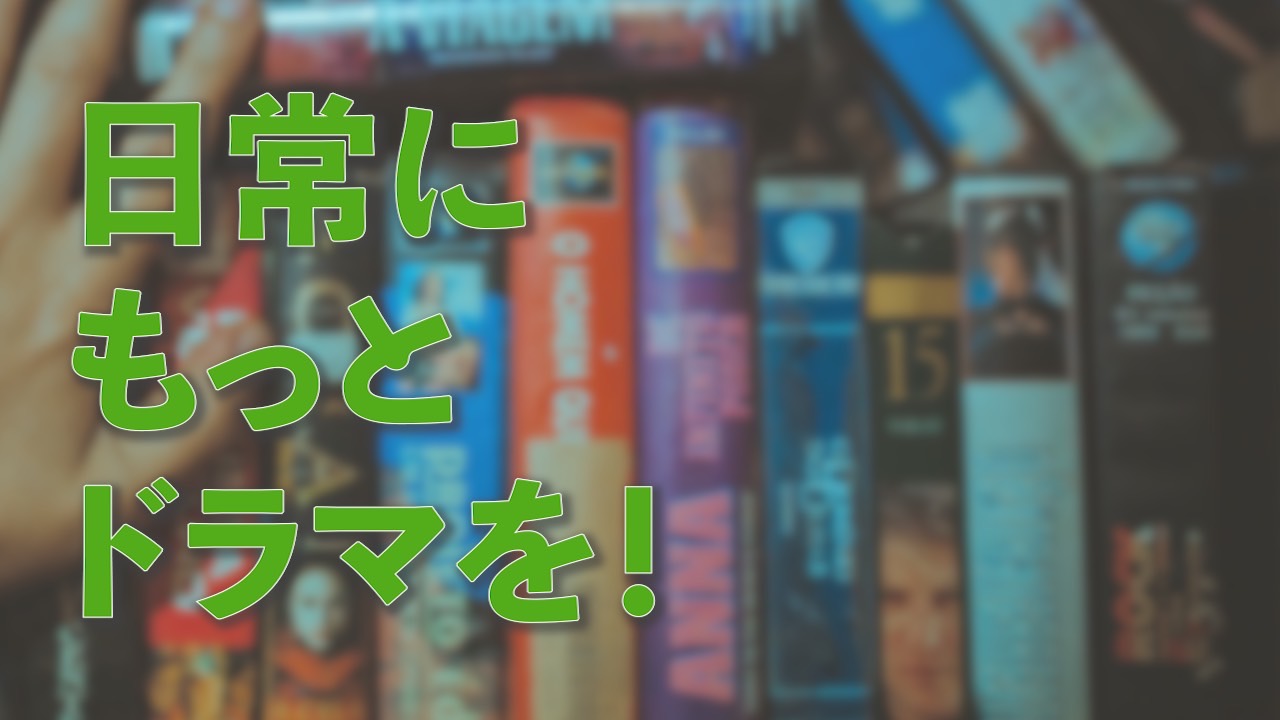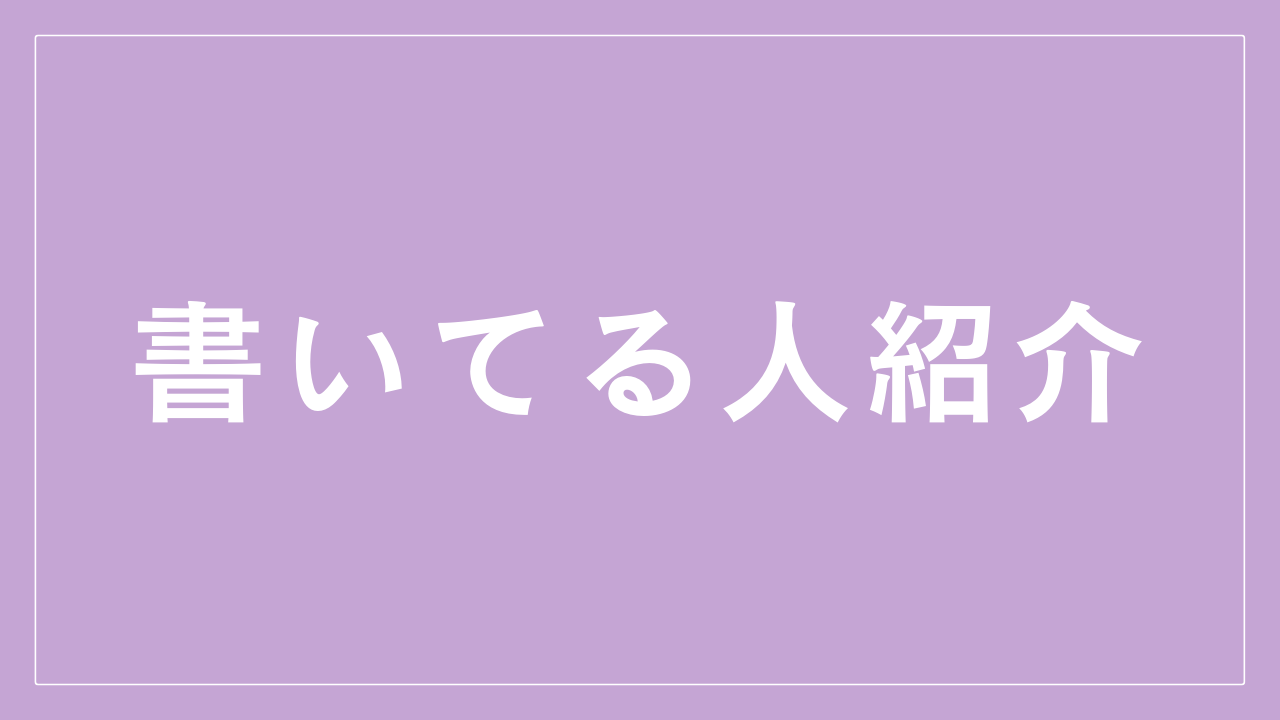文学と文化・社会との関係は,「文学は文化・社会につれ文化・社会は文学につれ」と言えよう。例えば,孝経の「孝莫大于严父,威父莫大於配天」という一文を私はあくまで文体の例として初めて耳にした。が,耳にした刹那,「家父長的だ」と,つい内容が前景化した。これに対するものでなくとも,儒教ひいては儒教的イデオロギーを俎上に載せてそれが家父長的だという指摘が,いくらかあると思う。そのような批評的視座は,儒教,中国,東アジアの文化を蔑視しているわけではないだろう。批評と非難・批判は違う。
文学は真空のなかで産出されない。言葉は社会と文化という空気中で発され,その呼気が空間に溶け,その変化した空気において,また発話がされる。すなわち文学はつねにすでに文化・社会を反映し,文化・社会へ反映される(実際には単純な往還関係ではなく,相互生成の関係であろう)。
このようなパラダイムでなされる象徴的な営為が批評だ。「そんな意図はなく普通に」文学を著わしたとして,その表現にはそのときの文化・社会の価値観が非意識的に普通に内在している。例えば上で私がフェミニスト批評的な読解を“つい普通に”したとて,それは「誤解を招いた」ということでも,穿った見方でもない。むしろ,よりニュートラルな読解であろう。警句に何気なくマチズモが包含されていたり,ある物語に何気なくジェンダーが表象されていたりするのである。少なくともそう読解できる。ナラティブ(語り/物語)には文化的・社会的な方向づけが“自然と”なされている。そのため,そうしたナラティブを受け取る際も,そのときの文化・社会に方向づけられていると考えられる。故に,そのことを踏まえて読むことこそがむしろ,穿った見方ではなく自然な(ニュートラルへと近づく)読解と思われる。