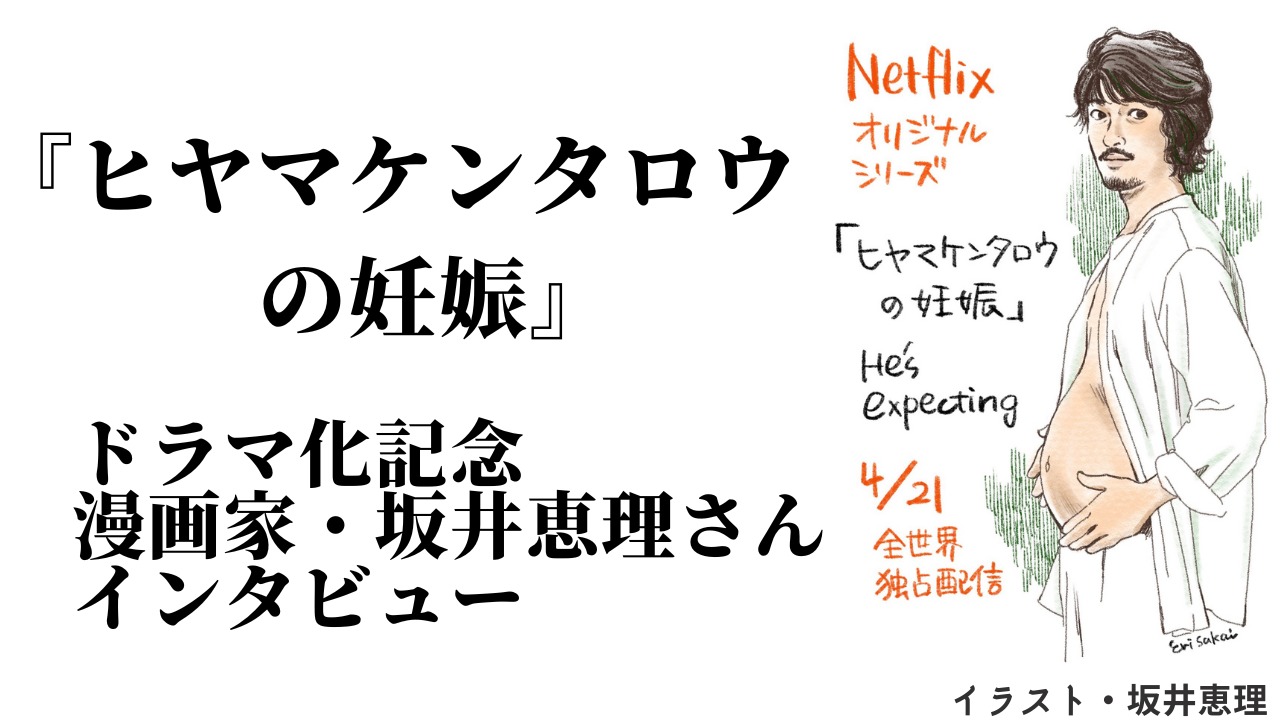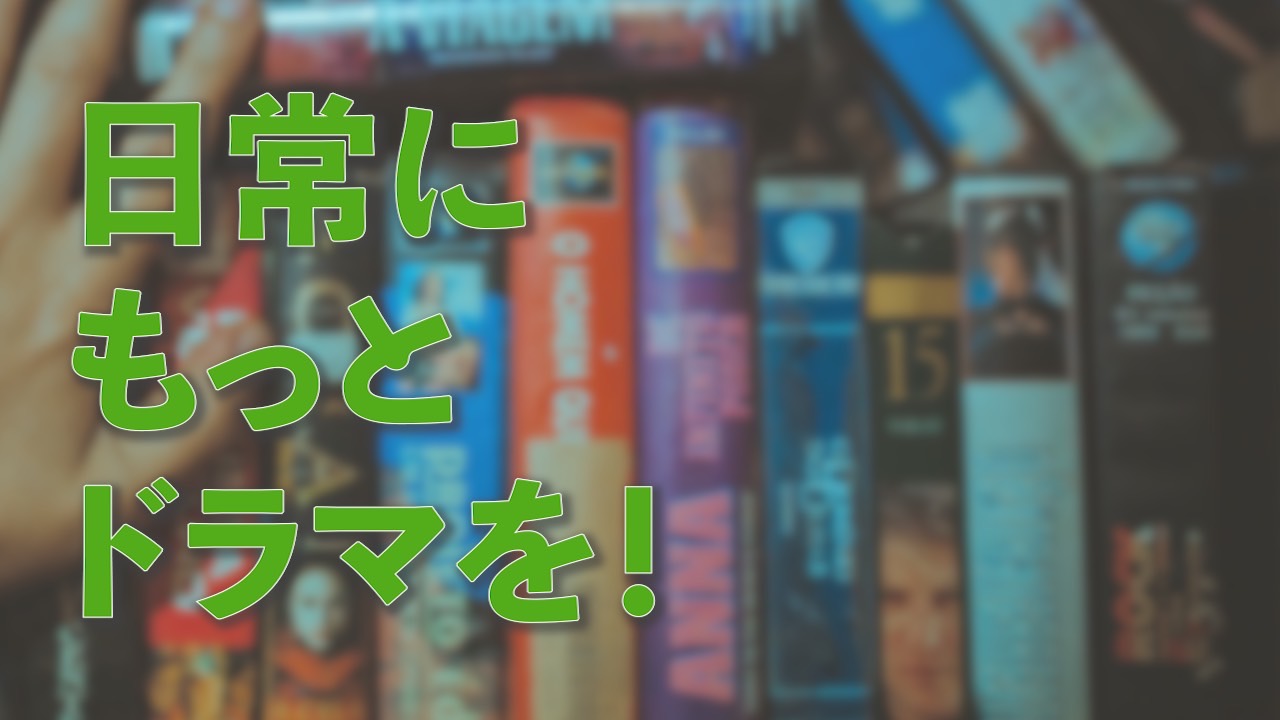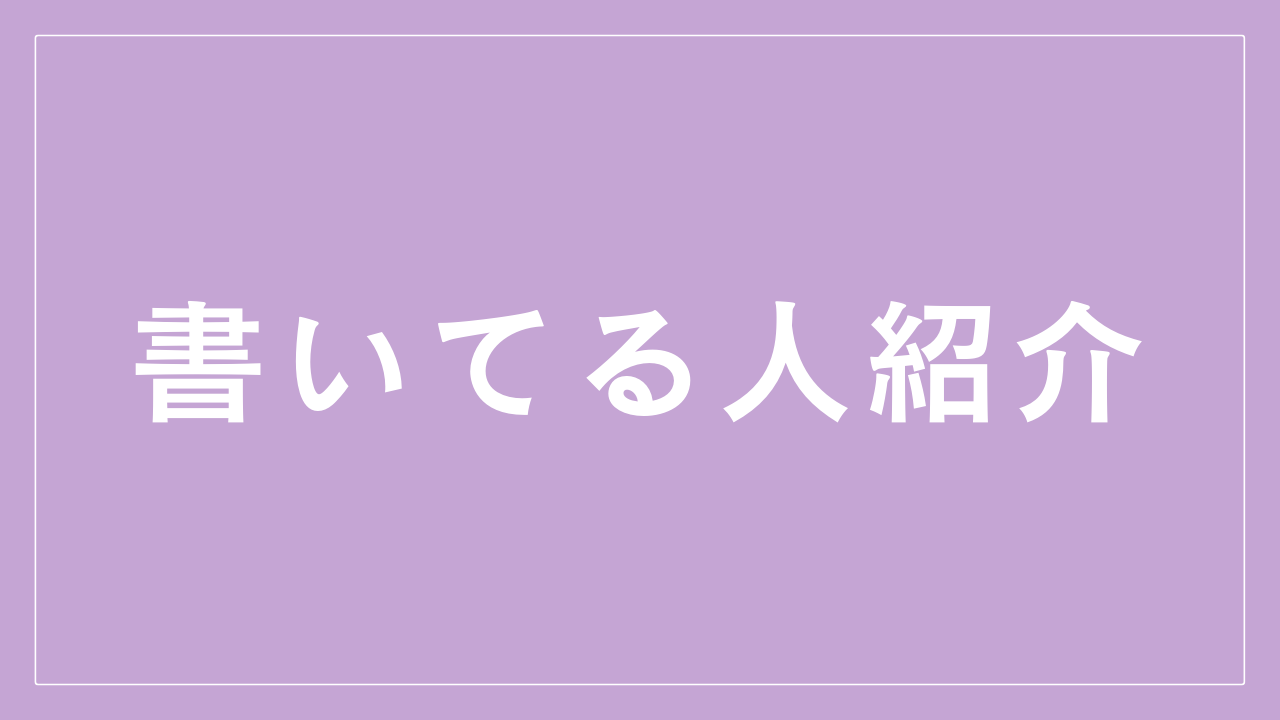22歳の秋。最近になってようやく自分がノンバイナリーのトランスジェンダーだと気がついた。
気付いた途端、それまでの事に納得した。
気付くまでは、ほら今だって履歴書とか殆どは男と女しかないし。自分で自分のことをどう思おうと、外部からは女として扱われるから、既にあった規範に仕方なく従っていた。
幼稚園の時、卒園式でフォーマルな手の置き方を男女別で教わったのを今でも覚えている。男子は両膝の上で拳を作り、女子は両手を三角に組む。なんで一緒じゃダメなんだろうと思った。言葉にはできなかったけれど、もやもやしていた。
それが自分にとってどこかが「違う」という事はわかっても、じゃあ一体何が自分にとって「正しい」のかということはなかなかわからなかった。
「違う」と漠然と思い続ける日々
私にとって、小学校は過酷だった。異質な存在だったから、頑張って擬態しようとした。
でも「違う」ことがあっても一体どこから合わせればいいのかわからないほど違いすぎて、結局擬態できなかった気がする。
女の子同士のなれ合いがよく分からなかった。好きな男の子とか憧れの芸能人とかリカちゃん人形とかの魅力が一ミリも分からなかった。
実はそれよりもダンゴムシを捕まえたり虫を育てたりする方が楽しかった。当時の私の近くには「虫愛づる姫君」のような女子はおらず、必然的にお気に入りの虫を見せたり一緒に捕まえたりするのは、虫に触れることを好意的に大人に受け止められ育てられているような男子とになった。
でも男子と遊ぶことは大人にとってあまり良くないらしかった。仲良くしていると当時の担任の先生から「夫婦」とからかわれた。「妻」じゃない。性別関係なくシンプルに遊んで何が悪いんだろう。
結局なにもよく分からなくて上手く馴染めなかった。
「男」でも「女」でもない時代の終わり
小学生の時は、あまり身体的にも性差がなく、そこまで自分の性別に関心を向けなくてもよかったような気がする。社会や大人からの期待や規範意識はあったけど。
そんな規範意識の中、私は一人称は「俺」がいいなと小学五年の時(周囲の一人称があたし、うち、私、みたいにフェミニンに変わりつつある時期だった)に思ったけれど、変に思われそうだからと押し隠していた。「俺女」は嘲笑の的だったから。心の中の一人称として使うに留めていた。
そうしているうちに冬になって、生理がきた。
自分が「女」の身体になっていくと理解した時、地に落とされたような気持ちだった。
空を飛ぼうとしていたのにその翼をもがれたような。なろうと思っていたものには永遠になれないと思い知った瞬間だった。
私にとって生理とは、私がなろうと思っていた、もしくはいつかなると予想していた未来が覆されたことの証明だった。自分が女性の身体であること、社会に割り当てられている性別が女性であることは知っていたが、いつかそれも終わるのだと思っていた。常識ではそうではないことを知っていたが、自分は例外だと思っていた。だから、生理が来たとき、とてつもなく焦った。
おいおいおいもう戻れないぞ。
人間の女としての人生、本格的に始まっちまうぞ。
焦ってももうどうしようもないし出来ないのだけれども。
「女の子のコスプレ」みたいな「擬態」
女として生きたいわけではなかった。
でもかと言って、男として生きたいわけでも特になかった。
どちらでもなく、ただただフラットに生きたかった。
でもそんな生き方のロールモデルなんて無かったから「女の子」としての人生しか残されておらず、もういっその事楽しんじゃおうと思って中高では思いっきり擬態した。
自分好みの、自分が一番可愛いと思う「女の子」になって、誰よりも「女の子らしい女の子」を演じてみた。コスプレみたいでそれなりに楽しかった。両親が「女の子らしい女の子」に育つことを望んでいたためその擬態は比較的容易だったし、「女の子らしい女の子」は社会のジェンダー規範と相性がよく、まあまあ居心地が良かった。
だけど、数年やって「あれ?これいつまで続くの??」という気持ちになりリタイアする事になる。
それからは「男も女も自分のラベルとして不適切な気がするな〜」と思いながら、自分と同じような「どちらでもない」人と出会えずに「自分の勘違いかも」と偶に不安になりながら悶々とした日々を過ごしていた。
LGBTQ+についての本でノンバイナリーというラベルを見つけたり、でもTwitterでトランス差別の「トランスジェンダーだと名乗るのは甘え」みたいな主張を目撃して「自分の勘違いなのかな」と思ったりして。でも、勘違いじゃなかったらしい。
ノンバイナリーだった。