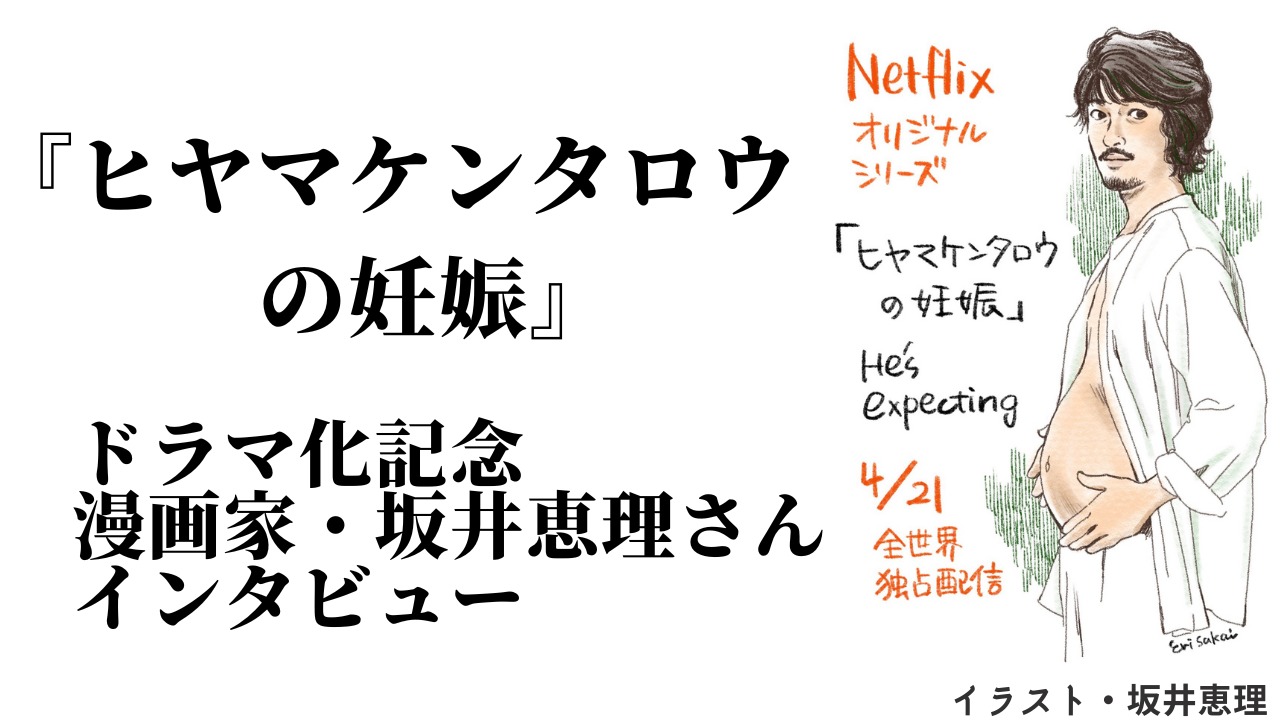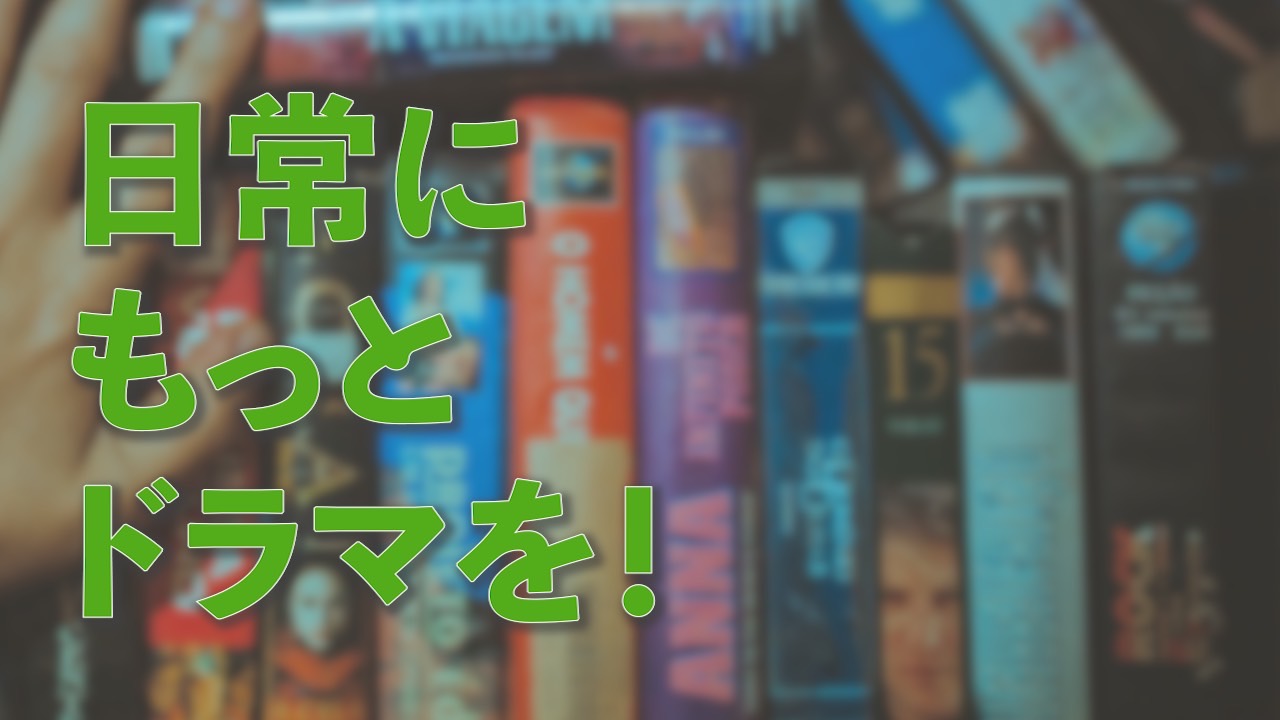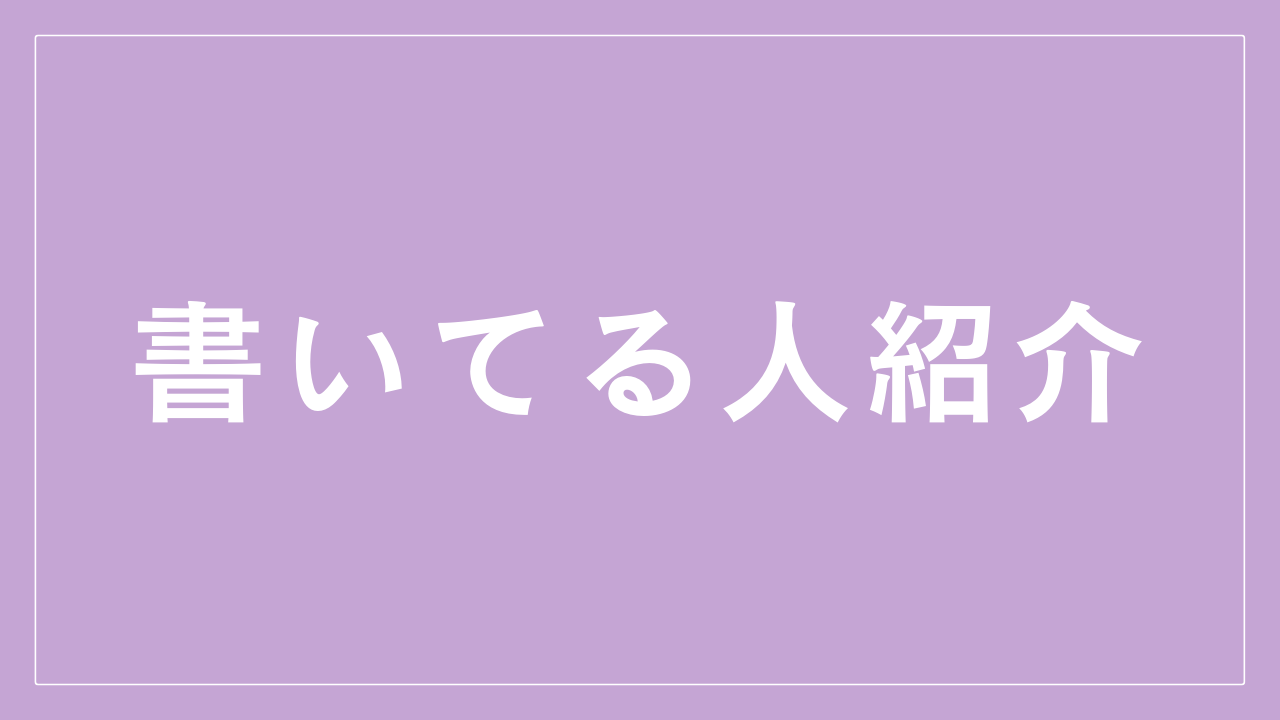サニタリーボックスの蓋を外すと、あのなんとも形容し難いむわりとした臭いが鼻腔をついた。ぼくは思わず顔を顰め、この陰気で暗鬱な作業をさっさと終わらせるべく、満杯になった黒いビニール袋を乱暴に引きずり出す。端をきつく結び、新しいものをボックスの内側に装着した。もう20年近く繰り返している作業なのに、どうしてか一向に慣れない。
正月休みの間に血祭りを迎えるのも、仕事始めに迎えるのもどちらも嫌で、考えた末に今回は連休中に終わるよう常用しているピルで調整した。月経移動を行うと、ピルの生理痛軽減効果はぼくの場合いささか薄れる。1日目は腹を下し、嘔吐した。激しく痛む腰にカイロを貼り付けると、ソファに投げ出していたiPhoneの画面に表示されたLINEの通知に気がついた。
送り主は母で、「祖母(父方)からお年玉を預かったから振り込んだ」という旨の連絡だった。通帳アプリをタップするとけっして少なくない額が増えていて、ぼくはげんなりした。ロキソニンを水で流し込み、ブランケットにくるまって蓑虫みたいにじっと痛みに耐える。じくじく痛む子宮は、ぼくをとことんまでに裏切り続ける。衣服を着ているのにも関わらず悪臭がそこから漂ってくるようで、また吐き気を覚えた。
あの日の祖母も、ぼくからこの臭いを嗅ぎ取ったのだろうか。
「生理が来たんなら、風呂はいちばん最後にしなさい」祖母が発した声は、タイル張りの古い台所に鈍く反響した。初潮がきた年の正月、例年通り父の実家に帰省していた。「でもこの子、いま生理が来てるわけじゃないんです」おそるおそる食い下がる母を、祖母は鼻で嗤う。「女になったんや。男の人らより先に入れさせられるわけないやろ」
祖母は、女が嫌いだった。自らもまた女であるにも関わらず、一族中のミソジニーを内面化しきっていた。嫁をいびり、姪をいびり、甥の妻をいびり、そして女になった「孫娘」──ぼくをいびった。ぼくの代では「女児」はぼくのみだったから、祖母のミソジニーは分散されることなくぼくに集中した。初潮を迎えると、それはますます顕著になっていった。
日本と韓国とロシアにルーツを持つぼくは、元在日コリアンでもある。父の実家は「在日コリアン」としてのアイデンティティを誇る人間が多数派で、儒教の名の下に男尊女卑と年功序列が正当化されていた。忘れ去れられた遺物のような風習は、家の「女」たちを常時ぎりぎりと締め上げ続けた。
血生臭さを纏うようになったぼくに対し、祖母はあからさま当たりがきつくなっていった。料理の手伝いを命じ、それでいてだれよりも早く食べ終わることを強いた。「女の子がたらたら食べるんもんじゃないの。後片付けせなあかんやろ」と耳元で怒鳴る祖母の吐息もまた、ぼくと同じく、いやそれ以上に、血生臭かった。そしてまた祖母は他の親族の前で、過剰にぼくの容姿を褒めそやした。「この子の肌は真っ白で綺麗やろ」「見て、まつ毛で頬に影ができとる」「こんな賢そうな顔つきの子、なかなかおらん」……こんな具合に、うっとりとした口調で。
男たちのために尽くし、男たちを支え、男たちに花を添える。祖母が望んだのは、男の従属物として不足のない──ただしけっして出過ぎてもない──、素晴らしく弁えた「孫娘」だった。ぼくはそんな祖母を心底軽蔑していて、現在のパートナーと結婚したきり会いに行くのをやめた。もう5年以上、顔を見ていない。
その「孫娘」が実は「女」でなかったと知ったら──しかも「女」とも寝る生き物だと知ったら、あのばあさんはどんな顔するんだろな。子宮の上を撫でる手を上に滑らせると、そこにふくらみはなかった。ふたつのふくらみは昨年の6月、タイで取っ払ってきた。それらはぼくにとって、単なるできものに過ぎなかったのだ。女でも男でもなく、また無性とも中性とも両性ともいえぬぼくのジェンダー・アイデンティティは、既存のカテゴリで表すならばノンバイナリーがふさわしい。
ぺったりとした胸を服の上から撫でていると、鼻の奥にまとわりついていた悪臭がやがて消えた。あの臭いは、呪いの臭いだ。ミソジニーの腐った臭い。そもそも生き物の体液なんだから、独特の臭いがするのは当たり前である。それを「呪い」たらしめているのは結局のところ、愚かな人間の妄想に過ぎない。血祭りが連れてくるどんよりした気分に呑まれると、そんな事実すらときどき忘れてしまう。
そのことに今も、祖母は気づかぬままなのだろう。だからたったひとりの「孫娘」に、いつまでも固執するのだ。金を使い、息子──父を使い、嫁である母を使い、再び手元におびき寄せようと糸を引く。息子しか持たない己の血を引く唯一の「女」が、理想の「女」に仕上がったかどうかをその目で確認しないと、夜も眠れない。あのひとは、そういう哀れなひとなのだ。
仕事を終えたパートナーが、書斎から出てくる。「大丈夫?」と心配そうに腹を撫でる手は温かく、ぼくをけっして「従属物」にしない。いつだってその手は、「個人」としてぼくを尊重する。
ぼくは生まれたときから、あなたの「孫娘」じゃなかった。そして二度と、未来永劫、再びあなたの「孫娘」を演じる日は来ない。そう心の中で呟きながら通帳アプリを開き、振り込まれたのと同じ額をそのまま母の口座へ戻した。