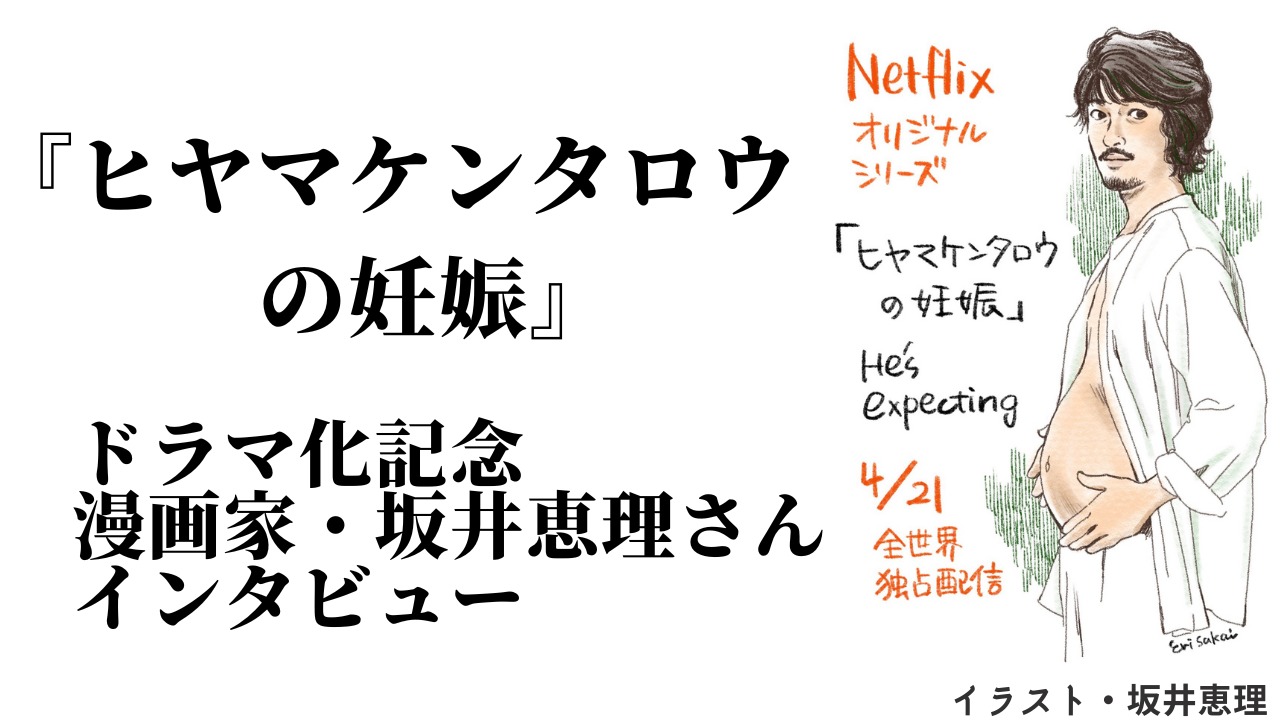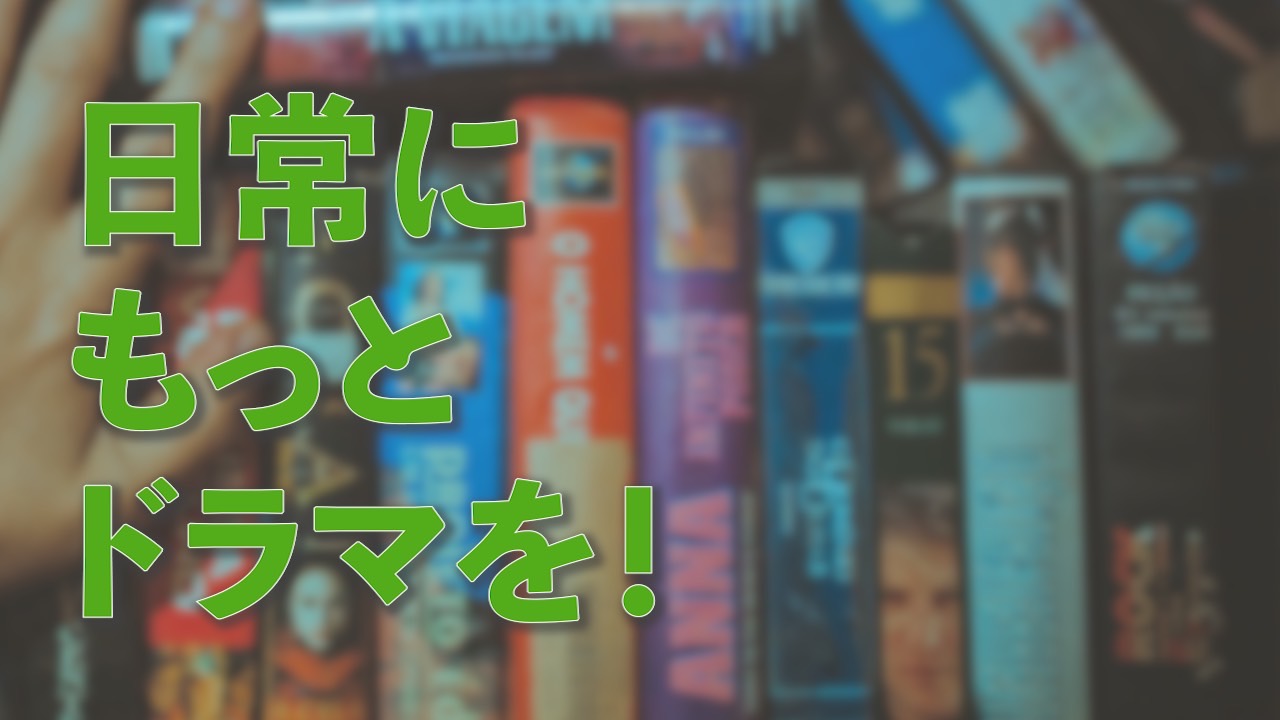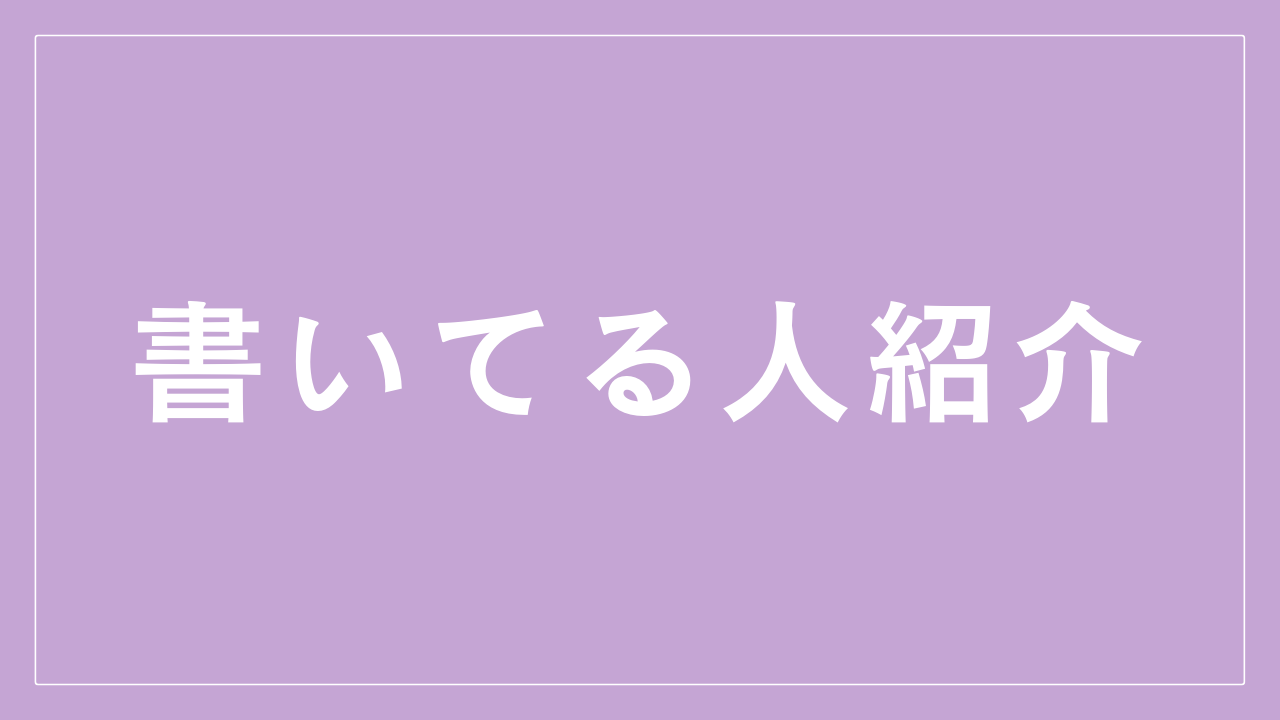コロナ禍でDVや性暴力が増えた。国や地域,洋の東西によって濃淡はあろうが,現在の世界はポストフェミニズム的な状況とは決していえない。現代においても文化・社会を越えて,しかしながらそれぞれの文化・社会固有の,男性優位主義・ミソジニーが遍在している。その好例がこの事実だろう。
女性に対する暴力の背景には,性欲ではなく(あるいはそれ以上に)支配欲・加害欲があるということが巷間よく言われている。そして,そのように男性から女性に支配のまなざしが向けられる基底に,家父長制があると考えられている。そのような社会規範・構造のただ中でコロナ禍が到来し,女性の失業や男性の在宅が(男性の失業と女性の在宅の増加以上に)増え,男性による女性への加害が増加した。このように,コロナ禍において女性に対して向けられる不平等な暴力や暴力的な不平等は各国・地域の当該社会における文化・規範と呼応していると考えられる。すなわち,コロナ禍の女性に対する不平等さは場所を越境してグローバルに遍在しつつも,その質や量は特異性を有すると考えられる。
たとえば法律学というディシプリンに対して私は,ジェンダー法学という領域/視座に関してとりわけその意味が前景化する。ジェンダー法学とは端的には現行の法律学ないし法律をジェンダーやフェミニズムの観点から脱構築する学問である,と私は理解している。近年,性交同意年齢や選択的夫婦別姓などがまた改めて俎上に載せられた。法律の制定・解釈は真空のなかでなされるわけではなく,つねにすでにそのときの社会の相互作用のなかで行われると思う。そのため,法律学を学ぶなかで現代の社会規範や倫理と呼応しない法規範が散見されることなどがあるだろう。その際に,聖書無謬説よろしく「法律無謬説」に依拠して法の無誤性を唱えるより,可謬主義的に逸脱を是正する。そのようなクリティカルな視座で法をそして社会を認識することにこそ,法律学を学ぶことの意義があるように私は思う。法ひいてはあらゆる明文はすなわち「明文化された規範」であり,規範は縦断的・横断的に異なるものである。規範がそうであるのと同じように,それに基づいて生じたものである制度や決まりやルールも,不変でも普遍でもないのだ。にもかかわらず,さまざまな物事が「今こうなっているからこれからもこうなっていくんだよ」という居直りの上で,「伝統だから伝統にしていくんだよ」というトートロジーで伝統にされていく。
私はあらゆる問題は,「結果の根拠化」という問題性に帰着すると思っている。たとえば,伝統的性役割(ジェンダー・ロール)の再生産を考えてみる。これは端的には,「女は(男は)そういうもん」として他人や自分の性ひいては生を規定する営みであろう。こうした態度には,あくまでジェンダー(社会文化的な営為としての性/社会文化的な営為の結果の性)に過ぎないものをセックス(生物学的な「そういうもん」)と捉えて根拠にするという,ジェンダーのセックス化/セックス視があるだろう。つまり,結果の性別を根拠の性別だと思ってしまうことの問題だと考えられる。
以上,コロナ禍においても顕現したミソジニーと,その基底にある規範と,その明文化である法や制度を,「結果の根拠化」という共通因数で約分しながら触れた。規範の変容による明文との距離を積極的に縮め,ミソジニーの行動化をゼロにしていくことが肝要ではないだろうか。